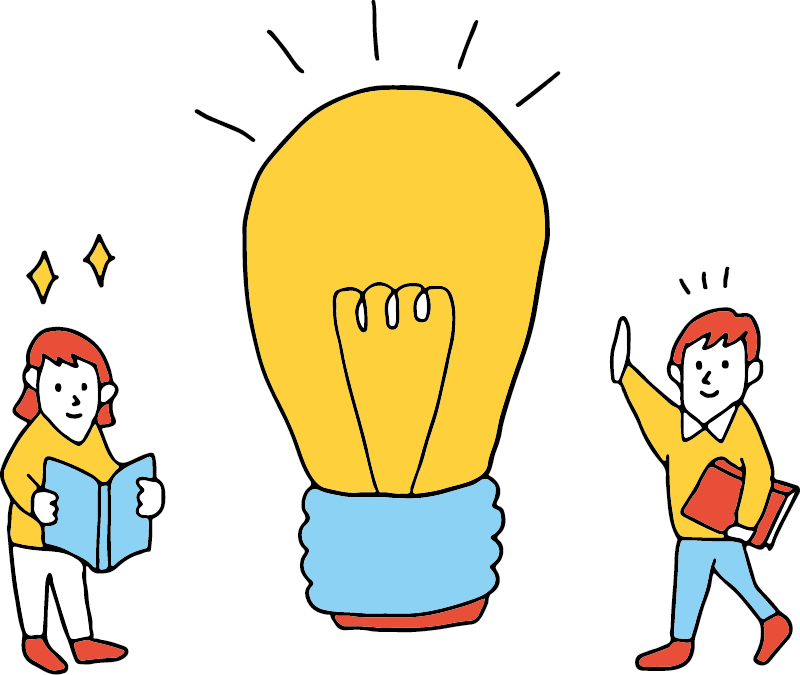香港の現状と将来について ~駐在経験から見た、報道では語られないビジネスの実像~
東京都中小企業診断士協会 城西支部のWEBサイトに私が寄稿したコラムが掲載されました。
(2025年10月22日)
引用元:
GlobalPlace 香港の現状と将来について ~駐在経験から見た、報道では語られないビジネスの実像~ | 国際業務支援 | 東京都中小企業診断士協会 城西支部
全文はこちら:
香港の現状と将来について
~駐在経験から見た、報道では語られないビジネスの実像~
国際部 鮫島 創
1. はじめに
2020年から2022年まで、私は前職で執行役員グローバル事業部長として香港に駐在し、香港子会社を始め、上海、バンコク、シンガポール、ジャカルタなど東南アジアの子会社・関連会社全体のマネジメントに携わりました。
この時期、日本国内では「国家安全維持法(国安法)施行を境に、香港は中国に完全に支配され、国際金融センターとしての地位を失いつつある」という論調が支配的でした。民主化運動の抑圧、外資企業の撤退、言論の自由の制限といったニュースが連日報じられ、「香港の将来は暗い」という見方が定着していったように思います。
しかし、実際に現地でビジネスを展開し、日々香港の街を歩き、現地スタッフや取引先と対話する中で、私が感じたのはそれとは大きく異なる現実でした。本稿では、実際に現地でマネジメントを経験した立場から、報道だけでは見えてこない香港の実像と将来の可能性について、異なる視点を提示したいと思います。

薄暮の香港島
2. 香港の現状(2020年代前半の姿)
私が駐在した2020年から2022年は、まさに国安法施行直後の時期でしたが、ビジネス環境という観点では、香港の本質的な強みは揺らいでいませんでした。
金融・貿易ハブとしての機能は依然として健在です。香港証券取引所でのIPO件数は世界トップクラスを維持し、国際的な資金の流れは途絶えていません。法人税率の低さ、自由な資金移動、英米法に基づく法制度の透明性といった、従来からの香港の魅力は損なわれていないのです。
特に私が実感したのは、東南アジア諸国との接続点としての強みでした。上海、バンコク、シンガポール、ジャカルタの子会社群を統括する立場として、香港の地理的優位性と人材の質の高さを日々痛感しました。香港からASEAN各国へのアクセスは良好で、時差も少なく、何よりも香港人材のバイリンガル能力と国際感覚は、地域統括拠点として理想的でした。英語、広東語そして多くの場合中国語を自在に操り、中国本土とASEAN双方の文化を理解するブリッジ人材が豊富に存在することは、他のアジア都市にはない大きなアドバンテージです。
ビジネス環境の変化はもちろんありました。規制の一部強化や、コンプライアンスへの要求水準の高まりなどです。しかし、これは香港固有の問題というより、世界的な潮流でもあります。むしろ重要なのは、こうした変化に対応しながらも、香港が持つ本質的な価値——国際ビジネスのプラットフォームとしての機能——は維持されているという点です。
3. 日本国内での誤解と実像のギャップ
日本で流布している「香港は中国に完全統合され、ビジネスの魅力を失った」というステレオタイプは、政治報道に過度に影響された見方だと言わざるを得ません。
確かに政治的自由の制約は現実です。しかし、企業活動や日常経済の実態は、報道から受けるイメージとは大きく異なります。
いくつか印象的だったエピソードを紹介しましょう。まず、YouTube、Facebook、WhatsApp、Googleなどが依然として自由に使え、世界中の情報にアクセスできることです。中国本土では規制されているこれらのサービスが、香港では何の制限もなく利用できます。ビジネス上のコミュニケーションも、日本や他の国々と全く変わりません。
国安法施行の直前、髪を切りに行った理髪店でのことも忘れられません。バーバーの若い男性が「私は本土のやり方が嫌いです。デモにも参加していました」と堂々と話していたことに驚かされました。もちろん政治状況は変化しましたが、このような率直な会話が交わされる空気が、今でも確かに存在しているのです。
そして、香港の人々が日本文化を心から愛していることも実感しました。銅鑼湾(コーズウェイベイ)やヴィクトリアピークの「ドンキホーテ」はいつも多くの香港人客で賑わい、日本の商品や文化への関心の高さを目の当たりにしました。街には相変わらず活気があり、レストランやショッピングモールは賑わい、スタートアップ企業も次々と生まれています。
私が関わった現地スタッフたちは、変わらぬプロフェッショナリズムで業務に取り組み、むしろコロナ禍という困難な状況下で、その柔軟性と対応力の高さを発揮していました。現地で肌感覚として得た「活力」と「柔軟性」は、東京の本社で見聞きする香港像とは全く異なるものでした。
ビジネスパーソンとして彼らと日々接する中で感じたのは、「報道される香港」と「実際にビジネスが動いている香港」の間には、埋めがたいギャップがあるということです。政治報道は重要ですが、それだけで一つの都市の未来を判断するのは早計です。ビジネスの現場では、規制環境、インフラ、人材、市場アクセスといった要素が実際の投資判断を左右します。そして、これらの観点から見た香港は、決して「終わった市場」ではありませんでした。
4. 香港の将来展望
香港の将来を考える上で重要なのは、その役割が変化しつつも、依然として不可欠な機能を持ち続けるという点です。
中国本土と世界をつなぐゲートウェイとしての役割は、むしろ強化される方向にあります。中国企業の国際展開、外資企業の中国進出、いずれにおいても香港の仲介機能は重要です。「一国二制度」が完全に消滅したわけではなく、法制度の独立性、資本移動の自由といった本質的な特徴は維持されています。
新たな成長分野も見えています。デジタル金融、グリーンファイナンス、バイオテクノロジーなど、香港政府は積極的に新産業の育成に取り組んでいます。金融テクノロジーのハブとして、また環境関連投資の拠点として、香港は新たな地位を確立しようとしています。
そして私が駐在中に特に実感したのが、ASEAN市場拡大に伴う地域ハブとしての重要性です。東南アジア経済の成長は今後も続き、この地域へのアクセス拠点としての香港の価値は高まるでしょう。中国とASEANの橋渡し役として、香港には他に代え難い地理的・文化的優位性があります。
もちろん課題もあります。一部の外資系企業の撤退や国際人材の流出は事実であり、企業活動の自由への懸念から、この動きに歯止めがかかっていない状況です。しかし、香港政府はこれに対し、積極的な人材誘致策や起業支援策で対処しようとしています。また、中国本土からの人材流入もあり、人材プールの質は依然として高水準を保っています。撤退企業の穴を埋める形で新たな企業も進出しており、ビジネス環境の基盤そのものが損なわれているわけではありません。
5. 中小企業にとっての示唆
では、日本の中小企業にとって、香港はどのような意味を持つのでしょうか。
第一に、香港を「中国市場への玄関口」として活用する戦略」は依然として有効です。直接中国本土に進出するリスクを避けつつ、香港を通じて中国市場にアプローチするという方法は、中小企業にとって現実的な選択肢です。法制度の透明性、英語でのビジネス遂行、資金回収の容易さなど、香港を経由することのメリットは小さくありません。
第二に、ASEAN展開を見据えた拠点活用です。私自身の経験から言えば、香港を地域統括拠点とすることで、東南アジア各国の子会社を効率的にマネジメントできます。中小企業が複数のASEAN市場に展開する際、香港に調整機能を置くことは戦略的に有効です。
第三に、パートナーシップ形成の観点です。香港には優秀な現地人材、信頼できる現地企業、国際的な金融機関が集積しています。単独での海外展開が難しい中小企業にとって、こうしたパートナーを香港で見つけることは、事業成功の鍵となります。
最も重要なのは、報道に偏らない、冷静な意思決定です。リスクを適切に把握することは必要ですが、過度に悲観的な報道だけを根拠に、ビジネスチャンスを逃すのは得策ではありません。実際の市場を見極め、自社にとっての戦略的価値を判断することが求められます。

マクリホーストレイルから望むロンケービーチ
6. おわりに
2年間の駐在経験を通じて得た私の確信は、「香港は決して終わった市場ではない」ということです。
政治的な変化はありました。報道される側面も事実の一部です。しかし、ビジネスの現場で日々動いている経済活動、変わらぬプロフェッショナリズム、そして将来に向けた新たな動きを目の当たりにした者として、私は香港の将来を悲観していません。
むしろ、日本の中小企業にとって、香港は依然として大きなビジネスチャンスを提供する市場だと考えています。中国市場へのゲートウェイとして、ASEAN展開の拠点として、国際ビジネスのプラットフォームとして、香港が持つ価値は色褪せていません。
今後も、城西支部国際部の活動を通じ、こうした海外の現場情報を会員の皆様と共有し、中小企業の国際展開を支援していきたいと考えています。報道だけでは見えない現実を、現場を知る者として発信し続けることが、私たち中小企業診断士の役割の一つだと信じています。
以上