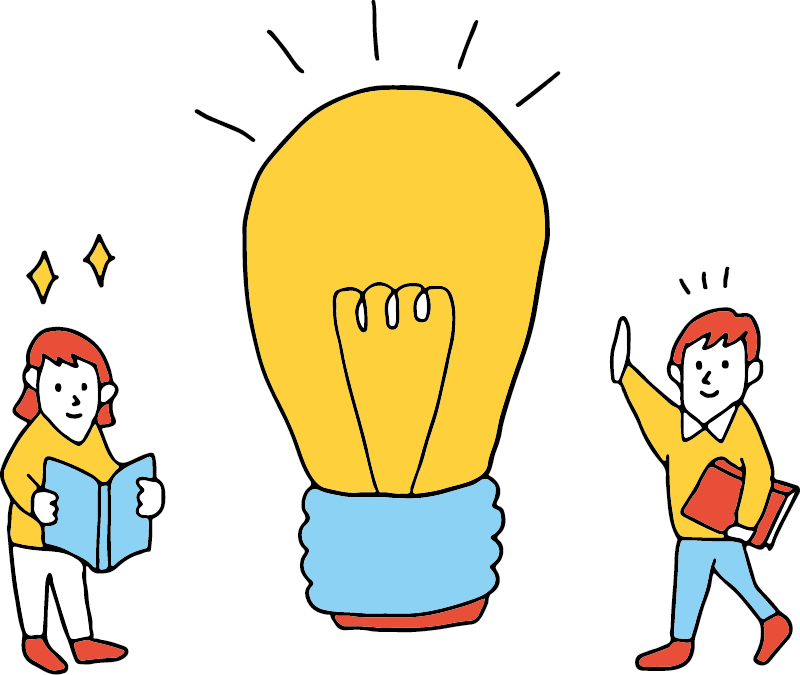生成AI考
2022年11月30日にChatGPTがリリースされて約2年半が経ち、多くの生成AIが様々な場面で活用されるようになってきました。
かつて「シンギュラリティ」(AIが人間の知能を超え、自らを改良し続けるようになる転換点)は2045年頃に訪れると未来学者レイ・カーツワイル氏は2005年の著書『The Singularity Is Near』の中で提唱しましたが、技術の進歩とそのスピードは我々の想像を遙かに超えていて、もはやシンギュラリティを迎えているのではないかと私は考えています。
私自身も経営コンサルタント業務で生成AIを使っています。有料のものは二つ。無料のものは4~5種類といったところです。例えば、企画書、提案書、マニュアル、フローチャート作成等々、従来なら何日もかかっていた作業がわずか数分でできてしまいます。これは私の生産性向上に極めて大きく貢献しています。今や生成AIなしでは業務は回らないと言っても過言ではありません。
もちろん、「だなどこ」(誰に、何を、どのように、狙う効果)や「5W2H」(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように、いくらで)などの基本的な情報を生成AIに与えなければ、アウトプットは漠然とした一般的なものしか出てきません。
従って、プロンプトの与え方が非常に重要だということです。また、プロンプトに投入する情報は主に対面コミュニケーションで得られた1次情報であることが重要です。インターネット上にあふれる3次情報をいくら生成AIに食べさせても、どれも同じような答えしか出てこないでしょう。
ですから、中小企業診断士の業務においても大事なのはクライアントとのF2Fのコミュニケーションであり、お客様との対話の中から情報を引き出すヒアリング力だということです。
さらに、注意しなければならないのは、生成AIは間違えるということです。私は複数の生成AIを用いてその答えの確からしさを常に比較・検討しています。機械が出してきたものを丸呑みするのではなく、「本当に正しいのか?」と検証することは人間にしかできないことだと思います。
同時に、生成AIはたとえそれが有料であっても情報セキュリティリスクがゼロではないと言われていますので、個人情報や企業名が特定できるような情報は入力しません。
つまり、生成AIはうまく活用すれば大いに頼りになる道具ですが、あくまでそれを使いこなすのは人間であり、生成AIの特性をよく理解した上で、使い方にはポリシーを持ち、習熟していくことが必要なのです。
ともあれ、生成AIの出現は私の仕事をポジティブな意味で大きく変えてくれました。今後も頼もしい相棒として付き合っていきたいと思います。