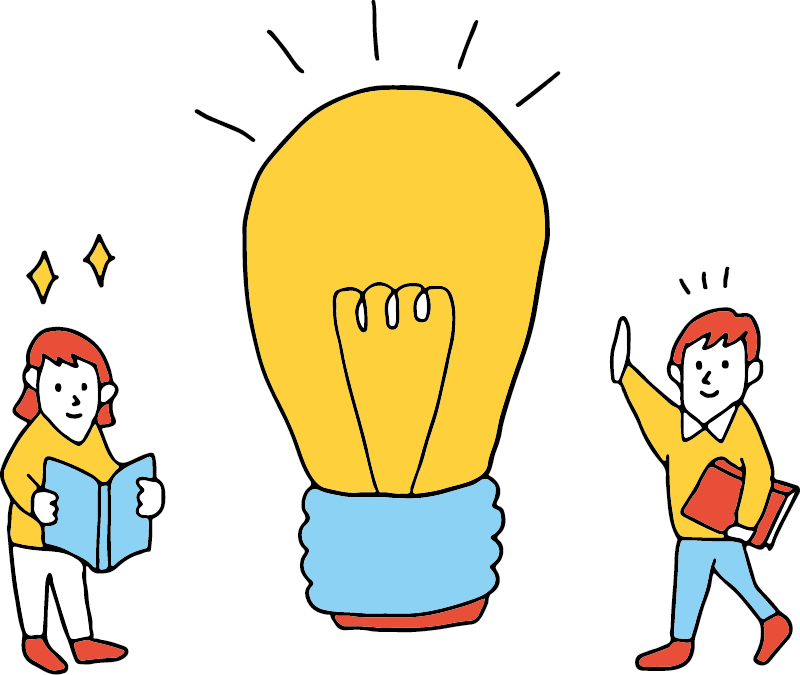なぜM&Aでは「セカンドオピニオン」が経営を守るのか
― 数字とストーリーの間で迷わないために
M&Aの検討が本格化すると、
経営者のもとには、さまざまな資料や提案が集まります。
- 事業計画
- バリュエーション
- スキーム案
- PMIのロードマップ
どれも一見すると整然としており、
「合理的な判断材料」が揃っているように見えます。
しかし、ここにこそ、
M&A特有の落とし穴があります。
M&Aの意思決定は「一度きり」である
M&Aは、
やり直しがきかない意思決定です。
にもかかわらず、
検討プロセスは短期間で進み、
限られた情報の中で結論を迫られます。
その結果、
判断の軸がいつの間にか、
- 提案資料の完成度
- アドバイザリーの説明力
- 周囲の期待や空気
といった要素に引き寄せられることがあります。
これは、
経営者個人の能力の問題ではありません。
構造的に起こりやすい現象です。
セカンドオピニオンの本当の役割
M&Aにおけるセカンドオピニオンは、
単なる「別意見」ではありません。
重要なのは、
判断の前提そのものを点検することです。
- その前提条件は現実的か
- 想定していないリスクはないか
- 楽観的な仮定に引きずられていないか
これらを、
ディールの成否とは距離を保った立場から
冷静に見直す役割が、
セカンドオピニオンです。
「妥当な価格」と「納得できる判断」は別物
バリュエーションが妥当であることと、
そのM&Aが経営として納得できるかどうかは、
必ずしも一致しません。
- なぜ今、このM&Aなのか
- 5年後に何を実現したいのか
- 想定どおりに進まなかった場合、耐えられるのか
これらの問いに答えられないまま、
「価格が妥当だから」という理由だけで
意思決定をしてしまうと、
後になって判断を説明できなくなります。
セカンドオピニオンが果たす「翻訳」の役割
実務の現場では、
アドバイザリーが提示する資料は、
高度に専門化されています。
その一方で、
経営者が本当に知りたいのは、
- この話は、結局どこが肝なのか
- 何を覚悟すべきなのか
- どこまで失敗を許容できるのか
といった、
経営判断に直結する論点です。
セカンドオピニオンの役割は、
数字や専門用語を
経営者の判断言語に「翻訳」することにあります。
GRCの視点がM&A判断を安定させる
前回のコラムで触れたGRCの視点は、
M&Aの判断においても有効です。
- 誰が最終責任を負うのか
- 失敗した場合、何が致命傷になるのか
- 守るべき一線はどこにあるのか
これらを事前に整理しておくことで、
M&Aの判断は
「勢い」や「期待値」から距離を保てます。
セカンドオピニオンは、
このGRCの観点から
意思決定を再点検する機会でもあります。
売り手・買い手、どちらにも必要な視点
セカンドオピニオンは、
買い手側だけのものではありません。
売り手にとっても、
- 提示された条件は妥当か
- 将来の関係性は持続可能か
- 自社にとって守るべきものは何か
を冷静に整理するために、
第三者の視点は有効です。
特に、
感情が入りやすい局面だからこそ、
距離を取った視点が
経営者を支えます。
おわりに
M&Aは、
「正解を当てる」意思決定ではありません。
不確実性を前提に、
どのリスクを引き受け、
どのリスクを回避するのかを
選び取る行為です。
セカンドオピニオンは、
その選択を
経営として説明可能な形に整えるための装置
だと考えています。
次回は、
M&AやPMIの最終局面で必ず問われる、
「人を任せる」という経営判断について、
掘り下げていきます。
海外子会社のガバナンスを考えるうえで、関連するテーマとして以下のコラムもあわせてご覧ください。
なぜ海外事業ではGRCが「管理」ではなく「経営の背骨」になるのか
【本稿について】
本稿は、筆者のこれまでのグローバル事業運営および経営支援の経験を踏まえ、
特定の企業・組織・時期を指すことのないよう、
事実関係を再構成・一般化したうえで記述しています。
実在の企業や個別事案を論評・評価する意図はありません。